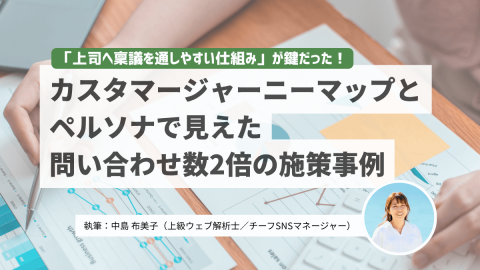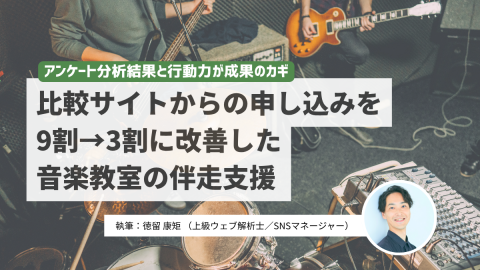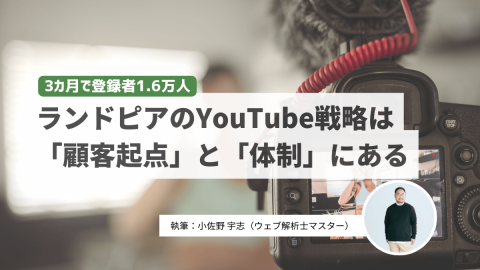こんにちは。ブランディング・マーケティングに関するコンサルティング事業を展開している、株式会社ピージェーエージェント代表取締役の加藤です。
弊社には、数多くの企業様から、「良い施策を思いついたのに続かない」「気付けば止まっている」というお悩みが寄せられます。SNS運用、記事作成、メール配信、広告運用、顧客フォロー施策。頑張って始めたはずが、数か月後には形骸化し、振り返れば“やらない理由”ばかりが積み上がっている。これは珍しい話ではありません。中小企業から大企業まで、業種を問わず多くの現場で起きています。
では、なぜ続かないのか。よく「担当者のやる気の問題」と誤解されますが、実際はそうではありません。マーケティングとは、短期では成果が見えにくく、中長期で積み上げることで効果が出る領域です。つまり「続ける前提」で設計された仕組みがないと、現場はすぐに本業の忙しさに飲み込まれます。担当者が優秀かどうかではなく、“止まりやすい構造”のままスタートしてしまっているのです。
施策が続かない企業には、共通点があります。
・目標は掲げるが、週次・月次単位のやるべきことに落ちていない
・属人化しており、担当者が忙しくなるとすぐ止まる
・成果が見えず、モチベーションが維持できない
・「継続よりも新しい施策」が優先されてしまう
本来、マーケティングは“一度やって終わり”ではなく、改善と育成の連続です。だからこそ必要なのは、才能でも気合でもなく「仕組み」と「習慣」。施策が止まらない企業は、“強い担当者”がいるのではなく、止まりにくい環境が整っています。
本記事では、“無理せずPDCAを回すための続けられる仕組み”に焦点を当て、すぐに取り入れられる具体的な方法をご紹介します。
よくある失敗パターン ― 続かない現場に共通する構造
多くの企業が最初につまずくポイントが、「目的」と「タスク」の距離です。たとえば、年間目標として「リードを○件獲得」「資料請求を前年比120%に」など立派なKPIを掲げているにもかかわらず、現場の週次業務に落とし込まれていないケースが非常に多いです。結果、「何から手を付ければいいか分からない」状態が続き、時間だけが過ぎていきます。マーケティング施策が続かない背景には、“戦略はあるのに、実行のプロセスが設計されていない”という構造が潜んでいます。
また、もう一つの大きなポイントが「属人化」です。担当者の頭の中にだけ進捗やノウハウが存在し、可視化されていない。すると、会議では施策が進んでいるように見えても、担当者が忙しくなった瞬間に一気に停止します。これは個人の能力や意欲の問題ではなく、“共有されていない仕組みの問題”です。
さらに、成果が短期的に見えにくいという性質も大きな壁になります。SNSやSEO、オウンドメディア、メールマーケティングなどは、結果が数字に現れるまで時間がかかるため、社内から「効果が見えない」「他の業務を優先しよう」と言われがちです。すると、続ける前に「やめる理由」だけが増えていきます。
また、「新しい施策ばかりに目移りする」ということも挙げられます。セミナーやSNSで新しい成功事例が出ると、「うちでもやろう」と手を広げ、どれも中途半端で終わっていく。マーケティングは“掛け算”ではなく“積み上げ”が効く領域なのに、積み上げる前に次へ行ってしまうため、成果が蓄積しません。
つまり、施策が続かない企業には、努力不足ではなく「続かない構造」が存在しているのです。
続けるための設計1:“無理なく回る”PDCAの仕組み
マーケティング業務において、「PDCAを回そう」と言われますが、現場ではこれが意外とうまく機能しません。その最大の理由は、PDCAが“理想型”で設計されすぎているからです。月次レポートは膨大、改善案は壮大、定例会議はやたら長い。これでは担当者が疲弊し、いつか止まります。大切なのは“完璧に回すこと”ではなく、“止まらない最低限のラインを整えること”です。
まず意識したいのは、「目標」と「行動」の距離を縮めることです。たとえば、「月間10件の商談獲得を目指す」という目標があるなら、週単位では「メルマガ2本配信」「広告を1回だけチューニング」「過去見込み客にフォローコールを10件」と、現場が手を出しやすい粒度にまで分解します。これが曖昧なままだと、施策は“やっている気がするだけ”になり、PDCAの前提が崩れます。
次に、進捗が見える仕組みを用意します。ExcelやGoogleスプレッドシートでも構いませんし、Trello、Notion、Backlogなどの無料ツールでも十分です。重要なのは、「誰が」「何を」「いつまでに」「どの状態で」進めているかが一目で分かることです。施策の管理表やカンバン方式は、想像以上に“止まりにくさ”に直結します。
また、改善会議は“短く、軽く、定期的に”を徹底します。1時間の定例会議を月1回行うより、15分の振り返りを週1回行う方が、PDCAは安定します。話す内容は「できたこと/できなかったこと/次にやること」だけ。資料も不要。 仰々しい会議をやめるだけで、現場の心理的負担は大きく減り、「改善」が日常になります。
そして、PDCAを“個人の責任”にせず、“チームのプロセス”として扱うことも大切です。人に依存するPDCAは必ず止まります。たとえ担当者が忙しくても、プロセスが存在すれば、最低限の運転は続きます。
重要なのは、「回したいPDCA」ではなく「回せるPDCA」を選ぶこと。これが、長く続くマーケティングの土台になります。
続けるための設計2:チームで習慣化させる仕組み
弊社のクライアント企業様の中で、施策が止まってしまう多くの現場では、担当者個人に業務が集中しているという特徴があります。「あの人がやってくれているから大丈夫」という状態は、一見スムーズに見えても、継続という観点では大きなリスクです。チームで習慣化させるために重要なのは、“特定の人が忙しくても止まらない仕組み”を用意することです。
そのために、まず大切なのは、業務の「見える化」と「形式知化」です。施策の進行状況、KPI、使っている資料、配信ルール、メッセージテンプレートなどを、担当者の頭の中ではなく、共有できる場所に置きます。フォルダ構成、命名ルール、施策ごとのチェックリスト、運用マニュアルがあるだけで引き継ぎは格段にスムーズになり、「担当者が抜けた瞬間に施策が消える」という悲しい現象を防げます。
次に、“成功体験をチームで共有”する仕組みも効果的です。例えば、メルマガで反応率が上がった、広告でCPAが改善した、ホワイトペーパーから商談が生まれた。こうした小さな成功は、担当者だけで抱え込むのではなく、必ずチームに伝える。成果を“チームのもの”として扱うことで、マーケティングが「個人の作業」から「組織の取り組み」に変わります。モチベーションに頼らずとも、続けやすい心理状態を作ることができます。
また、担当者同士で“レビューし合う”軽い文化も効果があります。LP原稿、メルマガ、広告文、バナーなどは、1人の主観で決めるより、複数の目で確認した方が品質も安定し、個人負担も減る。「自分だけが頑張っている」という状態は続きません。チームで支え合う設計こそが、習慣化の土台です。
そしてもう1つ重要なのが、“完璧主義を捨てる”こと。「100点でスタートしなければいけない」という思い込みは、現場を止めます。むしろ、60点で始めて改善し続ける方が、マーケティングでは圧倒的に成果が出る。チーム全体で「小さく始めて、続けて、改善する」を合言葉にできるかどうかが、成功の分岐点になります。
習慣化は精神論ではなく、仕組みの設計の問題です。強い担当者が必要なのではなく、「普通のメンバーでも続く状態」を作ることが、マーケティング組織を安定して成長させる鍵になります。
続けるための設計3:形式知化・テンプレート化・自動化の工夫
マーケティング施策が途中で止まる理由は、「考える部分」と「作業する部分」の区別が曖昧になっていることも挙げられます。毎回ゼロから考えるのは負担が大きく、続けられないのは当然。だからこそ、形式知化・テンプレート化・自動化は、継続のための最も強力な味方になります。
まず取り組みたいのは、“作業をテンプレート化すること”。たとえば、広告レポート、メルマガ配信記録、コンテンツ企画書、ホワイトペーパー企画、打ち合わせ議事録、週報・月報。毎回フォーマットが変わると手間も品質もバラバラになり、振り返りも困難になります。逆に「決まった型」があり、項目を埋めるだけで作業が完結する仕組みがあれば、属人性は下がり、スピードは上がり、再現性が生まれます。
次に、“意思決定ルールの形式知化”も有効です。「広告のCPAが基準を超えたら停止」「メールの開封率が目標以下なら件名をテスト」「記事は公開後2週間で検索順位を確認」など、判断の基準を最初から決めておけば、迷う時間が減り、担当者も動きやすい。経験の浅いメンバーでも、同じ基準で施策を進められます。
さらに、可能な部分は自動化してしまうことも大切です。Googleアナリティクスの定期レポート、広告アラート、メール配信のスケジューリング、CRMのステータス更新など、ツールを使えば“人がやらなくていい作業”は驚くほど多いものです。自動化によって「手が回らず止まる」を防ぐだけでなく、時間を“考える仕事”に回すことができ、結果的に成果とスピードが両立します。
重要なのは、「考えるべき仕事」と「型に乗せるべき作業」を切り分けることです。マーケティングは創造的な領域に思われがちですが、継続のコアは「標準化」です。型を作り、自動化し、再現性を持たせることで、誰が担当しても一定の品質で回り続ける。これが、“止まらないマーケティング組織”の基盤になります。
それでも止まってしまった時の考え方
どれだけ仕組みを整えても、現場には繁忙期やトラブル、突発タスクが発生します。マーケティング施策は、止まる時は止まります。大事なのは、「止めないこと」よりも、「止まった時に、どう再起動できるか」。実はここに、継続できる企業と、挫折してしまう企業の差があります。
まず意識したいのは、“止まったこと自体を責めない文化”です。「できなかった理由探し」や「担当者の能力の話」になると、誰も本音で言えなくなり、施策は静かに消滅します。重要なのは、事実を淡々と扱うこと。「できなかった理由より、次にいつ再開できるか」を決める方が建設的です。
次に、“再起動の仕組み”をあらかじめ準備しておくこと。
例えば、
・施策が止まったら、必ず「再起動会」を15分だけ行う
・その場で「次の一歩」だけ決める(大きな計画は作らない)
・タスクは最小単位まで削る
こうしたルールがあるだけで、何ヶ月も止まったまま、という事態は防げます。
また、「やらないことを決める」のも重要です。続けるためには、時に引き算が必要になります。「更新頻度を下げる」「配信チャネルを減らす」「レポート項目を簡略化する」など、“続けられる形にするための縮小”は、決して後退ではありません。むしろマーケティングは、負荷を最適化した方が継続性と成果の両立ができます。
さらに、“数字が見える状態”は、再起動の大きな助けになります。Googleアナリティクス、広告管理画面、MAツールなどで、「止まっていることで何が失われているか」が見えると、組織は自然と動き始めます。逆に、効果が見えない施策は再開されません。
そして、マーケティングは「やる気」で回すと必ず止まる、ということも、数多くの企業様のご支援をしてきた中で弊社が強く感じることです。必要なのは、“モチベーション管理”ではなく、“再開できる環境の設計”です。一度やめても、また戻れるという環境構築こそが、強いマーケティングチームの条件ではないでしょうか。
施策が続く企業には仕組みがある
マーケティングは「始めること」よりも、「続けること」の方が難しい業務です。SNS、広告、記事制作、メール配信、リードナーチャリング。どれも一度やっただけでは成果が出ません。結果が積み上がるのは“継続した先”です。しかし、多くの企業は「担当者のスキル」や「やる気」に依存してしまい、気付けば施策が止まり、振り出しに戻る。これは残念ですが珍しいことではありません。
しかし、逆のパターンも存在します。担当者が変わっても、繁忙期が来ても、トラブルが発生しても、施策が止まらない企業様がいます。それらの企業様は、決して「特別に優秀な担当者がいる企業」ではありません。共通しているのは、「続ける前提の仕組み」を持っていることです。
・目標を行動レベルまで落とし込む
・見える化と共有で属人化を防ぐ
・テンプレート化で作業を軽量化する
・自動化で“人間がやらないと動かない作業”を減らす
・止まったら、すぐ再起動できるルールを決めておく
この積み重ねによって、マーケティングは「頑張る仕事」から「淡々と回る仕事」に変わります。継続とは、才能ではなく設計の問題です。強い担当者一人がいることよりも、止まりにくい環境があることの方が、企業にとってはるかに価値があります。
この記事の内容を参考に、あなたの会社のマーケティングが、「止まらない仕組み」を持つきっかけになれば幸いです。