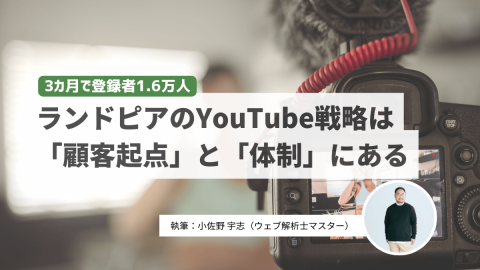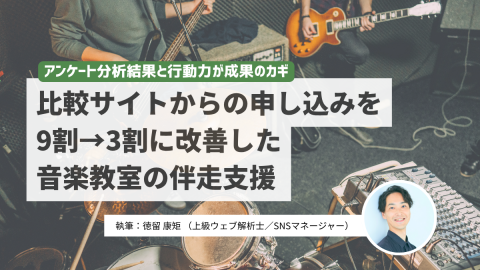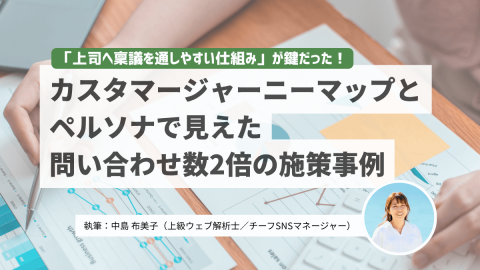こんにちは。ブランディング・マーケティングに関するコンサルティング事業を展開している、株式会社ピージェーエージェント代表取締役の加藤です。
コンテンツマーケティングの重要性が叫ばれて久しい現在、多くの企業が「自社の強みや知見を活かした情報発信」に取り組もうとしています。しかし、実際に動き出してみると、多くの企業が最初の壁にぶつかります。それが、「社内からコンテンツが出てこない」という課題です。
「うちには書ける人がいない」「現場の協力が得られない」「何を発信していいのかわからない」──特にBtoB企業を中心に、弊社にもよくご相談をいただきます。部署間の壁や業務の専門性の高さも影響し、マーケティング部門だけでコンテンツを生み出すことに限界を感じているケースが少なくありません。
その一方で、実際の業務現場には、顧客との接点や製品・サービスへの深い知見、日々の試行錯誤の中で得られた学びが、豊富に眠っています。もしそれらをうまく“引き出し”、発信できたなら、競合にはないリアルで信頼性の高いコンテンツが生まれるはずです。
本記事では、「書ける人がいない」「協力が得られない」と悩むマーケティング担当者・経営者に向けて、“巻き込み型”のコンテンツ制作術を紹介していきます。社内の理解を得る方法、協力を得やすい仕掛け、そして外部パートナーとの連携のコツまで、実践的なヒントをお届けします。 「社内にネタはある。でも形にできない」──そんなもどかしさを突破するヒントを、ぜひこの記事で掴んでください。
なぜ社内からコンテンツが出てこないのか?
コンテンツを社内で作ろうとしたとき、最初に直面するのが「誰も書いてくれない」「協力してくれない」という壁です。その原因は、単に「文章が苦手」「忙しいから」という表面的な理由だけではありません。背景には、いくつかの構造的・心理的な要因が存在します。
まず一つ目の要因は、「マーケティングの目的が十分に共有されていない」ことです。たとえば営業部門や開発部門にとっては、「なんで自分が記事を書く必要があるのか?」という疑問が拭えず、協力する意義を見出せないままになっているケースがあります。マーケティング施策の全体像と、その中でのコンテンツの役割を伝えきれていないことが多いのです。
二つ目の要因は、「文章を書くことに対する心理的ハードル」です。現場の社員が「自分の知見なんて大したことない」「文章を書くのは苦手」と感じていると、自信が持てずに前に進めません。特に完璧主義の傾向が強い文化では、「失敗したくない」という思いから筆が進まないこともあります。
三つ目の要因は、「成果が見えにくいことによる優先度の低さ」です。現場の多くは日々の業務に追われており、コンテンツ制作が直接自分の評価につながらない場合、どうしても後回しにされがちです。
このように、社内からコンテンツが出てこない理由は多面的です。つまり解決するには、「書き方を教える」だけでなく、動機づけや巻き込み方、役割の再設計といった工夫が必要になります。
マーケティング部門だけで戦わない発想
社内でコンテンツ制作を進める際、多くの企業が「まずはマーケティング部門で何とかしよう」と考えがちです。しかし、それではすぐに限界が訪れます。なぜなら、マーケティング部門だけでは「現場のリアル」や「専門的な知見」にアクセスしきれず、深みのあるコンテンツを生み出しにくいからです。
そもそも社内には、営業やカスタマーサポート、開発、商品企画など、顧客と直接向き合っている部署が存在します。こうした部署が日々の中で得ている情報や経験は、他社には真似できない“一次情報”の宝庫です。これをうまく活かさない手はありません。
そこで重要なのが、「コンテンツ制作はマーケティング部門の仕事」という固定観念を捨て、“全社的な情報発信チーム”としての発想に切り替えることです。といっても、全社員に記事を書いてもらう必要はありません。むしろ、各部門から「素材」を集め、マーケティング部門がそれを“料理”するような体制をつくることが現実的です。
たとえば、営業担当に「最近、お客様からよく聞く悩み」を共有してもらったり、開発担当に「製品のこだわりポイント」を語ってもらったりするだけでも、十分に良質なネタになります。これらをマーケティング部門が編集し、記事や動画などに落とし込めばよいのです。
つまり、「情報提供=現場」「編集・発信=マーケティング」という分業体制を意識することで、コンテンツ制作はぐっと現実的になります。
社内を巻き込むための実践テクニック
社内から協力を得てコンテンツを作るには、単に「記事を書いてください」と依頼するだけではうまくいきません。相手の負担感を減らしつつ、前向きに関わってもらうためには、“仕組み化”と“工夫”が必要です。ここでは、今すぐ実践できるテクニックを5つ紹介します。
① インタビュー形式で話を引き出す
文章を書くことに抵抗がある人でも、話すことには慣れているケースが多いです。そこでマーケティング担当者がインタビュアーとなり、専門知識やエピソードをヒアリングするスタイルに切り替えると、協力を得やすくなります。録音して文章化すれば、自然とコンテンツが生まれます。
② 依頼文のテンプレート化
「何を、どのくらい、いつまでに出せばいいか」が明確でないと、相手は動きづらいものです。依頼時にはテンプレートを用意し、「目的・テーマ・想定読者・文字数・締切」などを整理して伝えましょう。業務の合間でも対応しやすくなります。
③ 成果を“見える化”して共有する
「この前の記事が○○PVを獲得しました」「この記事を読んで商談につながりました」など、協力による成果をフィードバックすると、関係者のモチベーションは高まります。月次レポートや社内報で共有するのも有効です。
④ 企画段階から巻き込む
「書いてもらう」だけでなく、「どんなテーマが求められているか」のブレストに参加してもらうと、当事者意識が高まり協力を得やすくなります。意見を反映することで、コンテンツの質も自然と上がります。
⑤ 社内表彰やインセンティブを設ける
定期的に「ベストコンテンツ賞」などの表彰を行うと、関与する文化が社内に根づきやすくなります。金銭的なインセンティブでなくても、名前が出ることが喜ばれるケースもあります。
こうした工夫を重ねることで、社内協力は徐々に得やすくなります。
“書ける人”を育てる・発掘する仕組みづくり
コンテンツ制作を社内で安定的に回していくためには、「今すぐ協力してくれる人」を巻き込むだけでなく、“書ける人”を社内で育てたり、埋もれている人材を見つけ出したりする仕組みが必要です。
まず重要なのは、「文章力=ライターのようなプロレベル」でなくてもいいという認識を社内で広めることです。完璧な原稿でなくても、業務経験に基づくリアルな言葉は、読者にとって非常に価値があります。文法の整合性よりも、“現場の声”としての説得力が重視される場面は多々あります。執筆初心者には、「編集側で整えるので、まずは思ったことを自由に書いてください」と伝えるだけで、ハードルがぐっと下がります。
また、社内向けの「ライトな執筆体験の場」をつくるのも効果的です。たとえば社内SNSやイントラブログで、自由投稿の「ちょっといい話」や「最近の現場トピック」を募集してみましょう。そうした日常的な発信の中から、書くことに前向きな人や、表現のうまい人を見つけることができます。
さらに、“書くことが好きな社員”をリスト化し、ゆるやかな「社内ライターチーム」として育成するのも有効です。社内勉強会や、外部講師によるライティング講座を開くことでスキル向上も期待できます。実際に書いた記事に名前を載せたり、社内報で取り上げるなど、「見える承認」を与えることでモチベーションも高まります。
無理やり書かせるのではなく、「書いてもいいかな」と思える土壌をつくることが、継続的なコンテンツ制作には不可欠です。
外部パートナーとの上手な連携方法
社内からの協力や執筆体制に限界を感じたとき、頼りになるのが外部パートナーの存在です。専門のライターや制作会社などをうまく活用することで、コンテンツの量と質を安定的に確保することができます。しかし、外注すれば必ずうまくいくというわけではありません。成果を最大化するためには、「連携の仕方」が非常に重要です。
まず大切なのは、外部に丸投げしないことです。特にBtoB企業や専門性の高い業種では、外部の人間がいきなり書けるような内容は限られています。重要なのは、社内に眠る知見をいかに外部パートナーに“引き渡すか”という橋渡しの役割です。
たとえば、社内のキーパーソンとライターをつなぐインタビューの場を設定し、マーケティング担当がその場に同席して「意図」や「読み手像」を共有することで、精度の高い原稿が生まれやすくなります。また、事前にペルソナ・トーン・記事の目的をしっかりと伝える「編集ガイドライン」を用意しておくと、認識のズレを減らせます。
次に、継続的なパートナーシップを意識することも大切です。毎回ゼロから説明しなければならない関係では、効率も品質も安定しません。できれば継続して依頼し、企業理解の深まったパートナーと長期的に関係を築くほうが成果につながりやすくなります。
さらに、社内と外部をつなぐ“翻訳者”としてのマーケティング担当の役割も忘れてはいけません。現場の言葉を噛み砕いて外部に伝える、あるいはライターの文章を社内目線でチェックするなど、両者をつなぐ“ハブ”として機能することで、より価値あるコンテンツが生まれます。
こうした工夫を重ねることで、社内の負荷を抑えながら、専門性とオリジナリティのある情報発信を実現することができます。
さいごに
「コンテンツを作りたいのに、社内から何も出てこない」──これは多くの企業が抱える悩みです。ですが、決して“やる気のない会社”だからできないわけではありません。社内の誰もが本業に忙しく、コンテンツ制作が後回しになるのは当然のこと。だからこそ、“巻き込み型”の工夫や仕組みづくりが重要になるのです。
本記事では、協力を得られない根本原因を整理し、「マーケティング部門だけで戦わない発想」「社内を巻き込むための実践テクニック」「書ける人の育成・発掘」「外部パートナーとの連携方法」と、現場で役立つ実践的な考え方をお伝えしてきました。すべてに共通するのは、“一人で抱え込まず、仕組みで動かす”という視点です。
コンテンツは、会社にとっての「資産」です。広告と違って一過性ではなく、長く活用できるからこそ、社内の知見や現場の声を積み重ねていく価値があります。最初は時間がかかっても、巻き込み方の型ができれば、自然と回り始めます。
大切なのは、無理に「書かせる」のではなく、「話してもらう」「協力しやすくする」「成果を見せる」ことで、社内に小さな成功体験を積み上げていくこと。そして、自分たちだけでできない部分は外部の力を借りる柔軟さも持つことです。
「社内からコンテンツが出てこない」と悩む担当者・経営者の方々にとって、本記事が“次の一手”を見つけるヒントになれば幸いです。自社らしい言葉で、自社の価値を発信するコンテンツ制作に、ぜひ一歩を踏み出してみてください。