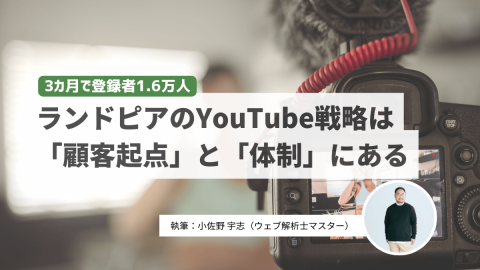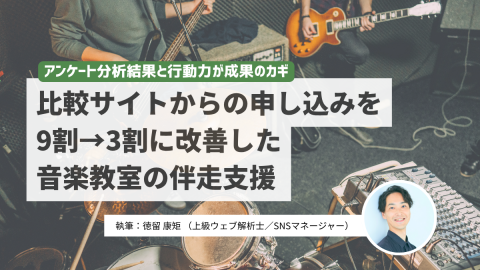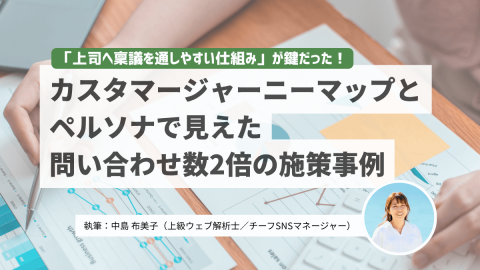こんにちは。ブランディング・マーケティングに関するコンサルティング事業を展開している、株式会社ピージェーエージェント代表取締役の加藤です。
マーケティング活動に対して、「それって売上に繋がっているの?」「本当に効果あるの?」といった声を社内から受けた経験はありませんか?
SNS運用、展示会出展、コンテンツ制作、広告配信―これらの施策は企業の成長に欠かせないものですが、短期的に成果が見えにくく、営業活動のように「数字」で説明しづらいという側面があります。
マーケティング部門は「お金を使うばかりで効果が見えないチーム」と認識されてしまい、経営層や他部門からの理解が得られにくいというお悩みが、様々な企業様から弊社にも多く寄せられます。特に、KPI(Key Performance Indicator)に表れないブランド価値の向上や、顧客との関係性構築といった“目に見えにくい成果”は、日々のレポートでは埋もれがちです。
しかし、だからこそ重要なのが「マーケティングの見える化」です。ただの数値報告ではなく、ストーリーや図解、現場の声を交えた“伝わる工夫”によって、マーケティングの価値を社内に適切に共有することが求められています。
本記事では、KPIでは伝えきれない成果をどのように可視化し、レポートとして落とし込み、社内理解を得ていくかについて解説します。
マーケティング活動が「伝わる」ことで、社内の信頼や協力体制が強まり、より大きな成果に繋がる。そんな好循環を生み出すヒントになりましたら幸いです。
なぜマーケティング活動は社内に理解されにくいのか
マーケティング部門は、企業の成長に不可欠な存在であるにもかかわらず、営業や開発など他部門と比べて社内からの理解を得にくい傾向があります。その背景には、いくつかの構造的な理由があります。
第一に、マーケティングの成果は「中長期的」であり、「間接的」なものが多いことが挙げられます。たとえば、認知拡大や見込み客の獲得、ブランドイメージの向上といった成果は、最終的な売上に繋がる重要なプロセスではありますが、営業のように即座に数字で示すことが難しく、貢献度が見えにくいのです。
第二に、マーケティング部門と経営層・他部門との“視点のズレ”も要因のひとつです。マーケティングでは「リード数」「コンバージョン率」「エンゲージメント」といった指標を重視しますが、経営層は「売上」「利益」「費用対効果」を求めます。この視点の違いが、レポート内容に対する納得感の乏しさや、意思決定のすれ違いを生むのです。
第三に、成果が「分業化」されている点も挙げられます。マーケティングが獲得したリードを、営業がフォローし、受注に至るという構造上、成果の功績が曖昧になりがちです。営業が成果を上げた際に、マーケティングの貢献が見過ごされることも少なくありません。 こうした背景から、マーケティング部門は「何をしているか見えにくいチーム」として扱われがちです。理解を得るためには、こうした構造的なハードルを意識したうえで、「見える化」を意図的に行っていく必要があるのです。
KPIでは測れない「本当の成果」とは?
マーケティング活動において、KPIは重要な指標です。Webサイトの訪問数、リード獲得数、広告のクリック率など、成果を数字で管理し、PDCAを回す上では欠かせません。
しかし、KPIだけでは語れない成果が、マーケティングには数多く存在します。
例えば、ブランド価値の蓄積です。継続的なコンテンツ配信やSNSでの発信、広告出稿によって、顧客の中に「信頼できそうな会社」という印象が形成されていくプロセス。これは明確な数値として表れにくく、社内でも見過ごされがちですが、最終的な購買行動に大きな影響を与える重要な資産です。
コンテンツや仕組みの蓄積も、KPIでは測りづらい価値のひとつです。たとえば、オウンドメディアに掲載した記事が検索流入を長期的に生み出したり、ホワイトペーパーが営業現場で繰り返し活用されたりするようになると、それは「使い回し可能な営業支援ツール」として企業の武器になります。このような“再利用可能な資産化”は、時間をかけて効いてくる成果です。
また、「顧客理解の深化」も挙げられます。マーケティング活動を通じて、どんなテーマに反応があるのか、どのチャネルで接触すれば反応率が高いのかといった“顧客インサイト”を蓄積していくことは、商品開発や営業戦略にも活用できる重要な情報です。
このように、マーケティング活動の価値は、数字に現れない部分にも存在します。見えにくいからこそ、どのように言語化し、社内に共有していくかが問われるのです。
マーケティング活動を“見える化”する3つのポイント
マーケティングの成果は、意識しなければ見えづらいものです。だからこそ、他部門や経営層に「何をして、どんな変化があったのか」を的確に伝える工夫が必要です。ここでは、見えにくいマーケティング成果を“見える化”するための3つのポイントをご紹介します。
成果を「ストーリー」で伝える
数字の羅列では、施策の意味や背景は伝わりません。「何を課題と捉え、どんな打ち手を行い、どのような変化が起きたのか」というストーリーを添えることで、施策の意図や価値が明確になります。
たとえば、「ホワイトペーパーのダウンロード数が増加した」という数字だけでなく、「営業から『提案時の信頼性が増した』という声があった」といった定性的な変化を伝えると、施策の手応えが伝わりやすくなります。
ビジュアルで表現する
図やチャート、フローチャートを使って視覚的に表現することで、マーケティング部門以外の人にも成果が伝わりやすくなります。たとえば、カスタマージャーニーに基づく施策と接触ポイントの図解、チャネル別のリード獲得比率の比較グラフなどは、「どの施策がどこで機能しているのか」を一目で伝えるような工夫をしましょう。
共有の頻度と方法を工夫する
月1回の定例レポートだけではなく、社内ポータルなどで、週次・日次で“小さな変化”を共有する仕組みを作ることで、マーケティング活動が日々動いていることを社内に浸透させることもできます。また、レポートをメール添付するだけでなく、直接説明する「報告会」や「社内勉強会」を併用することで、相手の理解度を高めることも可能です。
社内レポートで成果を伝える際の工夫
マーケティング活動の価値を社内に正しく伝えるには、「レポートの内容」だけでなく「見せ方」や「伝え方」が大切です。どれだけ優れた施策を実行していても、その意義や成果が伝わらなければ評価や協力が得られません。ここでは、弊社が普段クライアント企業様にアドバイスしている、「社内報告の際に意識すべき工夫」をご紹介します。
伝える相手ごとに“見せ方”を変える
経営層、営業部門、商品開発など、部署ごとに関心は異なります。
たとえば経営層には「意思決定の材料」となる要約やインパクト重視のグラフを中心に、営業には「提案に使える顧客情報」や「ホットリードの特徴」、開発部門には「顧客のニーズや課題の傾向」など、相手の目的に沿った情報を優先的に提示することが効果的です。
定量と定性をバランスよく
数字ばかりでは味気ないし、現場の声ばかりでも主観的すぎる—だからこそ、定量データ(リード数、CPA、CVRなど)と定性的な成果(顧客の反応、社内の声、営業のフィードバック)を組み合わせて伝えることが重要です。
「この施策で○件のリードが獲得され、営業から“商談化しやすいリードが増えた”との声も上がっている」など、具体例を交えると説得力が増します。
図解・テンプレート化でわかりやすく
「接点別リード獲得数の推移」や「ファネル別のCVR比較」「キャンペーンごとのROI」などは、表やグラフで視覚的に示すと一目で伝わります。毎月使えるテンプレートを用意しておくと、継続的な共有がスムーズになり、社内でも“マーケの動きが見える化されている”という認識が浸透していきます。
社内を巻き込む「共感型マーケティング報告」のすすめ
マーケティングの成果を社内に伝えるうえで、ただ“数値”を報告するだけではなかなか理解を得られません。難しいとは思いますが、できるだけ関係者の「共感」を引き出す報告スタイルを意識することが大切です。単に「結果」を伝えるのではなく、「現場のリアル」「人の感情」「変化のストーリー」を盛り込むと、共感を生む報告に近づくと弊社では考えています。
たとえば、展示会での成果を報告する際、単に名刺の獲得枚数や案件化率を共有するのではなく、「あるお客様が、以前配信したメルマガをきっかけにブースへ訪れてくれた」というエピソードを加えると、関係者にとって自分事として感じられる情報になります。このような“顔が見える成果”は、数字では伝えきれない説得力を持ちます。
また、営業やカスタマーサクセスといった他部門の声をレポートに反映させるのも有効です。たとえば「今回のリードは提案しやすかった」「お客様の反応が良かった」といった現場の声を盛り込むことで、マーケティング活動が社内の“共通の成果”であることを印象づけられます。
さらに、「一緒に取り組んでいる」という姿勢を示すことも重要です。営業との定例ミーティングで成果を共有したり、次の施策の方向性をすり合わせたりすることで、他部門との連携が深まり、マーケティング活動が社内全体の取り組みとして受け入れられやすくなります。
共感型の報告を意識することで、単なる“情報共有”から“仲間づくり”へと進化します。マーケティング部門が社内で孤立するのではなく、信頼され、協力される存在になるために、報告の中にも「人の熱量」を織り込んでいきましょう。
さいごに
マーケティングの価値は、目に見える売上や数値だけでは測れません。顧客との関係性を築き、ブランドの信頼を高め、将来の売上に繋がる“仕込み”を行うことが、マーケティングの本質的な役割です。にもかかわらず、その成果は社内では見過ごされがちで、正しく理解されないまま評価が下がったり、リソースが削られたりすることもあります。
だからこそ、マーケティング担当者自身が、自らの活動を“見える化”し、その価値を社内に伝える努力をすることが大切です。KPIや数値にとらわれすぎることなく、ストーリーや図解、現場の声などを組み合わせて、「伝わる報告」を行うことで、社内の理解・信頼・共感を得ることができます。
本記事で紹介したような、相手の関心に合わせた見せ方、定量と定性のバランス、共感を呼ぶエピソードの活用などを、日々のレポートや会話の中に取り入れてみてください。
マーケティング部門だけで孤軍奮闘するのではなく、社内を巻き込み、営業や商品開発と連携してこそ、より大きな成果が生まれます。その第一歩は、「伝え方を変えること」から始まります。 あなたのマーケティング活動が、社内に正しく理解され、より多くの人に応援される存在になることを願っています。