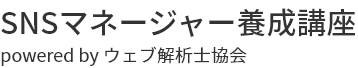交流が進むXスペース運営の3ステップ
投稿日:2025年9月10日

チーフSNSマネージャーの久保田善博です。
WACA会員部副部長、関東支部副支部長として資格更新のためのフォローアップ講座を開催したりしております。また事業推進部地方DX委員会では、全国の商工会議所や自治体の相談室で中小企業や団体の皆さまの伴走支援をしています。SNSをどう活用すべきか迷う担当者に寄り添い、現場で実行できる戦略や運営の型を共に作り上げることを大切にしています。これまで、BtoB企業や協会組織のSNS活用を支援し、参加者同士の交流が自然に生まれる場づくりに取り組んできました。
今回はSNS運営に役立つ実践知識をお伝えします。
忙しい人こそ音声配信がおすすめ
投稿や分析に追われる中で「もっと交流を深めたい」「発信を継続したい」と悩むSNS担当者におすすめなのが、音声を活用した場づくりです。特にX(旧Twitter)の音声ライブ配信機能「Xスペース」は、企業や団体の交流促進に大きな可能性を秘めています。
テキストや画像と違って生の声でのやりとりは強いつながりが生まれやすく、しかも顔出し不要で気軽に参加できる点が参加ハードルを下げます。運営者にとっても続けやすい仕組みです。
交流を進めやすい運営の「型」
イベントを立ち上げるだけでは人は集まりませんし、集まっても交流が深まらなければリピーターは育ちません。そこで、今日から実践できるXスペース運営の「型」をご紹介します。
以下の3ステップで準備しましょう。
(1)テーマの設計
参加者が「自分ごと」として関われるテーマの設定が第一歩です。
(2)交流の仕掛け
スペースにはリスナーがコメント(投稿)することもできます。コメントを取り上げたり、スピーカーとして発言するよう促したりして聞いている全員が参加できるよう工夫しましょう。発言してもらえば積極的に関与、つまりエンゲージメントしていることにもなります。
(3)改善の反映
開催後に必ず振り返りを行い、分析ツールの結果や参加者の声を次回に反映させます。
チェックポイント
1. テーマ選定の工夫
- 投票やアンケートで参加者にテーマを決めてもらう
- 季節やトレンドを盛り込む(「今年の振り返り」「新年の抱負」)
- 課題感に直結する内容を用意する(「炎上から学ぶSNS運営」)
2. 告知と集客の仕掛け
- 開催中に次回イベントを告知する
- インフルエンサーや専門家とのコラボで新規参加者を呼び込む
- クチコミしたくなる仕掛けを用意する。参加しやすい雰囲気が大切
3. 交流の運営術
- コメントを会話に取り入れ、双方向性を高める
- スピーカー登壇を歓迎する雰囲気を整える
- リピーターへの感謝を伝え、安心して参加できる場を作る
ポイントは主体性と改善
交流が進むXスペース運営のポイントは、特別な技術ではなく参加者の主体性を引き出すことと改善を続けることです。
まずは、テーマ選びをひと工夫してみてください。会話の深まり方が大きく変わり、参加者が「また聞いてみたい」と感じてくれるはずです。